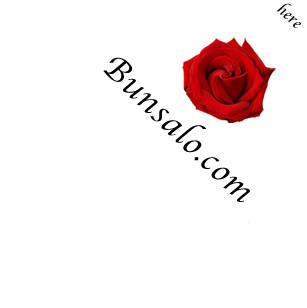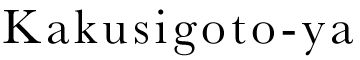羽田野直子です。リアリティーについて
みなさんはどんなときにリアリティーを感じますか?
ここ数年、私はリアリティーについてずっと考えています。
そもそも今教えに行っている映画学校の学生が書くシナリオを読んでいて疑問を抱き始めたのがきっかけです。
普段おとなしそうでやさしい学生が意外にも「暴力」を描こうとする…その理由を考えていて行き当たったのがリアリティーです。
今の学生たちの世代は子どもの頃から「仮想現実を構築するさまざまな装置」によって、実感(リアリティー)というものに当たるというある種の皮膚感覚が後退してしまった世代だといえると思うのです。
その結果、彼らが暴力という形で実感(リアリティー)を描くのではないかという仮説に辿り着いたのです。
リアリティーっていうとまず「ほんとうらしさ」ということが頭に浮かびます。
我々のように映画やドラマで虚構の世界を作ることを生業とする者は観客が「嘘くさい」と思わないようにとその「ほんとうらしさ」にこだわります。
でもそのことが「仮想現実を構築するさまざまな装置」と何ら変わらないとしたら…。
例えば我々が「それはお話の世界のこと」と割り切っていた現実と非現実の境界線について今の子どもたちは極めて曖昧な認識しか持っていない気がしてなりません。
そんなとき、確か去年のお正月明けだったと思いますが、
『彼女の名はサビーヌ』というドキュメンタリー映画
に出会いました。
『仕立て屋の恋』に出ていた女優、サンドリーヌ・ボネールが自閉症の妹(サビーヌ)を撮影した作品です。
ほんの10年前には美しい娘だった(過去の8ミリ映像も時々インサートされます)サビーヌが適正な診断と治療を受けられず、抗精神病薬の大量投与やきびしい拘束によってまるで別人に変貌してしまった。
30キロも体重が増えてよだれを垂らす、その悲惨な姿をカメラはしずかにとらえます。
姉であるサンドリーヌがようやく見つけた専門の施設で回復の兆しをほんのわずかに見せ始めているサビーヌの日常。
彼女はカメラのこちら側にいる監督というより姉の存在に安心しているのがわかります(一度だけ、不在のときに撮っていますがやはり様子が違いましたから)。
撮影対象との距離感が近いという意味でドキュメンタリーの常道でいうとそれは珍しいことですが、いわば愛のあるその距離感がこの作品の観客を辛い思いからぎりぎり救っていたとも言えます。
そうしてこのドキュメンタリーフィルムが映画になる瞬間がありました。
それまで時々インサートしていたサビーヌの20歳そこそこの映像をある日サンドリーヌ監督がサビーヌ自身に見せるのです。
若いサビーヌが夢見たアメリカへの旅行。
目がキラキラしてほんとうにきれいです。
別人のような現在のサビーヌがそれを見ています。
そして声をあげて泣き出します。
サンドリーヌの「辛いのなら止めようか?」の問いかけに激しく頭をふって「うれしいから泣いてるの!」と言うサビーヌ。
震えるほど心を揺さぶられました。
こうした真実の力を目の当たりにすると「ほんとうらしさ」は吹っ飛んでしまいます。
先日から映画美学校で『世界のドキュメンタリー』という講座が始まりました。
初回が私の大好きなポルトガルの映画監督、ペドロ・コスタでしたし、対談相手が諏訪敦彦監督だったので迷わず申し込んで通い始めました(奇遇にも『彼女の名はサビーヌ』を見たのは映画美学校の試写室でした)。
リアリティーについて考えるために何かヒントが得られればと期待して。
行ってみたらやはり学生ばかりで私がひとりでここの平均年齢をあげてるな(笑)と思いましたが、いくつになっても知りたいこと、見たいものがあったら…といつかこのブログでも書きましたから平気でした。
面白くて引き込まれてすっかりそんなことは忘れてしまっていました。
第一回の成果についてはまた次回に。