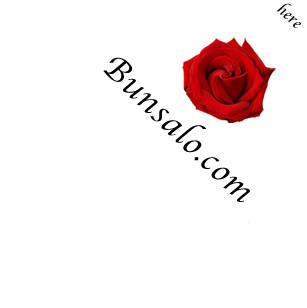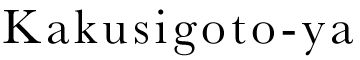羽田野直子です。恋について!
恋は生きていくためのエネルギーになりますが、ときにひとを絶望の淵に追いやる凶暴さも秘めていて、それはある意味甘美な罠ともいえるでしょう。
「運命の恋」とか「永遠の恋」といわれる恋。
それはひとが一生のうちに何度かおちるほかの恋とどう違うのでしょうね。
「いきなり何を言い出すのだ、このひとは」と怪訝に思われるでしょうが、いま公開中のアルゼンチン映画『瞳の奥の秘密』を七月に観て以来、そのことをずっと考えていました。
最初にこの映画試写の招待葉書を見て「昔のハリウッド映画みたい」という印象を抱きましたが、それは当たっていたように思います。
この映画の主人公は裁判所を定年でリタイアしたベンハミン。
彼には忘れられない事件があります。
それは新婚間もない、うら若く美しい妻の暴行殺人事件。
彼は元上司のイレーネにそれを小説にしようしていると告げにいきます。
彼女の笑顔に浮かぶ不安な影…。ふたりは何かを共有していることが伺えます。
そしてベンハミンの彼女への想いは25年経ったいまも彼の心の底から離れることなく、だからこそ件の事件も記憶の底に消えることがないのでしょう。
彼が小説にするために真実を求めていく課程で胸の奥深くに沈めていたはずの彼女との忘れ得ぬ恋がいま現在のものとして彼の心の中で息を吹き返します。
事件の起きた1974年(アルゼンチンは軍事政権下にありました)と2000年のいまを往ったり来たりしながら物語は進んでいきます。
国の複雑な事情を背景に、飽きさせることなくしかも最終的には観客に人間の罪と罰の問題を突きつけるまさにウエルメイドな「昔のハリウッド映画」です。
アカデミー賞の最優秀外国語映画賞も受賞したそうです。
目新しさはないが人間の姿や社会の矛盾がきっちり描かれている、この映画は八月半ばから公開されました。
特段宣伝に力を入れている節も見当たらないのに地味ながらも話題になり、しかも結構なロングラン(十月半ばまで)になっています。
それで冒頭の問いに戻ります。
惚れたはれたの恋ではない恋、「運命の恋」や「永遠の恋」。
それは他のひととは絶対に共有できない何かをともに見つめたり、志向することができる恋でしょう。
そのことでたとえ、ふたりが窮地に追い込まれるようなことがあったとしても、世俗的な意味でしあわせになれなくとも…というまさにパッション(この言葉には情熱と受難というふたつの意味があるのです)そのもののような恋。
この映画をめぐる現象を見ていて、そのような恋に「映画で」とはいえ実はみなさん惹かれるのだなと改めて思ったのです。
「そんなの当たり前!」と言うなかれ、みなさんかなり現実的な「条件」をおっしゃるではありませんか(笑)。
作り手側が観客動員のために目新しい何かを開拓しようと躍起になっている一方で、『瞳の奥の秘密』のような映画を見たいひとが思いの外、大勢いたというこの事実はやはり人間の根底に真実や理念を求めるという本質が備わっている証左だと考えて、まだまだ捨てたものじゃないなって気になりました。
ただ恋愛ドラマに障壁は必須条件でそれが難物である度合いが高ければ高い程いい(盛り上がる)のです。
『瞳の奥の秘密』には軍事政権下という恰好の障壁がありました。
現代の日本で恋愛の障壁を求めるのは至難の業です。
そうして今日もどこかで作家や脚本家は頭を抱え込んでいるのです。