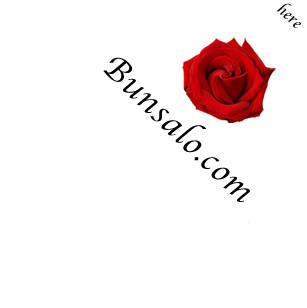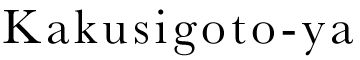羽田野直子です。新年の映画はブラジル映画で!
ご無沙汰してしまいました。
秋以降、試写室や映画館、
そして映画祭でさまざまな映画と出会ったのに。
また折にふれてそれらについても書いていきます。
さて、新しい年を迎えて一本目はブラジル映画『名前のない少年、脚のない少女』でした。
まず思ったのはよくぞこの映画を買ってくれましたということ。
主人公は「ささやかな夢を抱いた人々」が住むブラジルの田舎町の少年。
ネットに「ミスター・タンブリンマン」のハンドルネームで自作の詩を投稿して都会に住むチャットの相手と話し、またネット上に公開されているいかにも生命力の薄い美少女の写真や動画を見るのが日常。
自分のエネルギーをどこへもぶつけられず、この町を出たくても出られない、たとえ出たとしてもその先に何かが拓けてくるという未来さえ信じられない少年の不毛な焦燥感。
監督はティーンエイジャーのその生の心情にどこまでも寄り添い、映像と音楽だけで時間も空間も変幻自在に飛び越える、まさに映画というジャンルでしか描き得ない世界観を徹底的に描いているのです。
喪失感と絶望でしか結ばれていない友だちとの関係や、彼にとって絶望の象徴であり、同時にある種の神秘性を持った青年との関係が次第に明らかになっていくけれど、だからといって何も変わらない現実。そう易々とは動いていかないストーリー。
この作品はいまの多くの人たちが映画だと思っているその枠からは明らかに外れています。
だからこそ、「よくぞ…」と思ったわけです。
折しもシネセゾンの閉館というニュースが飛び込んできましたし。
国の勢いが衰えたからか、最近の若者は冒険心が薄れてしまっていると言われています。
その彼らはヨーロッパやアメリカ、アジアへ旅をしたいと思わないだけでなく、映画もハリウッドのものでさえ行かないらしいのです。
彼らがこの作品をどう見るのか。
いい作品だけどみんな見に行ってくれるのかしら…そう心配してしまうのが悔しい。
試写室を出て食事を済ませて街を歩きながら、自分の子どもの頃に思いを馳せました。
私は小さい頃ひどい乗り物酔いに悩まされていました。
中学生になった頃から次第に克服できたのに、時折不調に見舞われると真っ先に
「ああ、こんなことではまだ見たことのない広い世界へ行くのは無理だ、飛行機に10時間以上も乗るなんて…」
と暗澹たる気持ちになったものです。
日曜の朝『兼高かおる世界の旅』を見ていたからそう刷り込まれたのではなく、大人になったら自分が見たいと思ういろんな世界を見てやろうと無意識に思っていたのでしょう。
ふとこの『名前のない少年、脚のない少女』は20代の人たちよりもミドルティーンやハイティーンの子たちが見るといいなと思いました。
映画というものが意識の中で確立されていない(ある意味毒されていない)彼らにこそ、この映画はすうっと受け入れられるのではないかと。
そうしてまた映画というものの可能性を信じている監督たちがマーケティングに縛られない映画作りに打ち込める余白が広がるように願わずにはいられません。
あ、でもこれを読んだ方の中には「よおし、見に行こうじゃあないか!」という方もいらっしゃると思います。
是非そうしてください。
この作品は思春期から青年期に移るときの不安定なあの感じを思い出して目眩がします。
胸が苦しくなります。
そういう生の感情に出会える稀有な作品です。