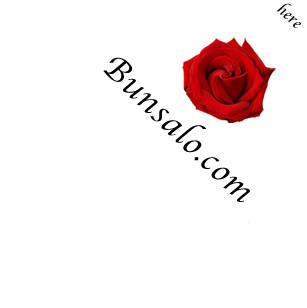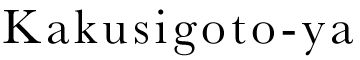『レイチェル・カーソンの感性の森』http://www.uplink.co.jp/kansei/という映画を見てきました。
レイチェル・カーソン(1907-1964)はノーベル平和賞を受賞したアル・ゴアが「彼女がいなければ、環境運動は始まることがなかったかもしれない」と賞賛したことによって再び注目を集めた、『沈黙の春』(1962)を書いて化学物質の環境へ与える影響についての問題意識を人々に呼び起こした女性です。
この作品はカイウラニ・リーという女優がレイチェル・カーソンの著作や活動に感銘を受け、一人芝居の脚本として仕上げ、18年間演じてきたものをインタビューに答えながら海辺の別荘での暮らしぶりをインサートする、ドキュメンタリー形式で映画化したものです。
毎度のことながら受付で渡された資料をほとんど読まないで映画に向かうので、私はてっきりこれがドキュメンタリー映画だと思って途中まで見ていました。そして、はたと気づいたのです。レイチェル・カーソンはうんと昔の、白黒しかない時代のひとだった—つまりこれはドキュメンタリーではないと。
クリストファー・マンガー監督は妻に勧められて見た舞台に感動したものの、当初映画化は難しいと随分逡巡しながらカイウラニ・リーと話していくうちにドキュメンタリーのスタイルでというアイディアに辿りつき、製作に着手したそうです。
海のそばの別荘と家、実際レイチェル・カーソンが生活した場所でたった五日間の撮影の前に監督とカイウラニ・リーとの間で演技についての随分綿密なやり取りがあったようです。なぜなら舞台での演技とドキュメンタリーらしく撮るための演技はまったく異質のもののはずだからです。
18年もの長い間レイチェル・カーソンを演じてきたカイウラニ・リーのいわゆる役作りは完璧だったでしょうけれど、舞台で観客を惹きつけるための動きやセリフ回しなどをそのまま映像に持ち込むとオーバーでぶち壊しになりますから、たぶん現地入りする前に何度もリハを行ったのだと思います。
結果としてこの映画は成功しています。
一旦これは再現したものでドキュメンタリーではないとわかったあとも、そのことを忘れてしまう瞬間が幾度となくありました。そして家族と縁の薄いレイチェル・カーソンが死を目前にしてたったひとりこの世に残さなくてはならない唯一の血縁である息子(亡くなった姪の忘れ形見を養子にした)のことを思い、またやり残したことや生への断ち切り難い執着で胸が塞がり哀切極まる姿にもう現実と虚構の境目は消えてしまいました。
カイウラニ・リーはレイチェル・カーソンが憑依しているかの如く、映像の中で彼女の生を生きていました。
現実と虚構の境目を超えるということ—このことは映画の本質を表しているといえます。映画の始まりのとき、リュミエール兄弟の蒸気機関車の映像を見て観客は思わず逃げそうになったといいます。観客が映画に求めるもののひとつにリアリティがあります。そもそも映画はドキュメンタリーから出発したのですから。
ポスプロによって作られた虚構のリアリティが広がる中、この映画は俳優の身体、そしてそれを真っ直ぐに捉えたカメラによってその原点に回帰したすばらしい作品だといえるでしょう。
カイウラニ・リーが長年続けてきた舞台の題名は『センス・オブ・ワンダー』、レイチェル・カーソンの著作の題名でもあります。
みなさんも感性と想像力の翼を拡げていま一度映画の原点に向き合ってみてください。
『レイチェル・カーソンの感性の森』 という映画を見てきました。
レイチェル・カーソン(1907-1964)はノーベル平和賞を受賞したアル・ゴアが「彼女がいなければ、環境運動は始まることがなかったかもしれない」と賞賛したことによって再び注目を集めた、『沈黙の春』(1962)を書いて化学物質の環境へ与える影響についての問題意識を人々に呼び起こした女性です。
この作品はカイウラニ・リーという女優がレイチェル・カーソンの著作や活動に感銘を受け、一人芝居の脚本として仕上げ、18年間演じてきたものをインタビューに答えながら海辺の別荘での暮らしぶりをインサートする、ドキュメンタリー形式で映画化したものです。
毎度のことながら受付で渡された資料をほとんど読まないで映画に向かうので、私はてっきりこれがドキュメンタリー映画だと思って途中まで見ていました。そして、はたと気づいたのです。レイチェル・カーソンはうんと昔の、白黒しかない時代のひとだった—つまりこれはドキュメンタリーではないと。
クリストファー・マンガー監督は妻に勧められて見た舞台に感動したものの、当初映画化は難しいと随分逡巡しながらカイウラニ・リーと話していくうちにドキュメンタリーのスタイルでというアイディアに辿りつき、製作に着手したそうです。
海のそばの別荘と家、実際レイチェル・カーソンが生活した場所でたった五日間の撮影の前に監督とカイウラニ・リーとの間で演技についての随分綿密なやり取りがあったようです。なぜなら舞台での演技とドキュメンタリーらしく撮るための演技はまったく異質のもののはずだからです。
18年もの長い間レイチェル・カーソンを演じてきたカイウラニ・リーのいわゆる役作りは完璧だったでしょうけれど、舞台で観客を惹きつけるための動きやセリフ回しなどをそのまま映像に持ち込むとオーバーでぶち壊しになりますから、たぶん現地入りする前に何度もリハを行ったのだと思います。
結果としてこの映画は成功しています。
一旦これは再現したものでドキュメンタリーではないとわかったあとも、そのことを忘れてしまう瞬間が幾度となくありました。そして家族と縁の薄いレイチェル・カーソンが死を目前にしてたったひとりこの世に残さなくてはならない唯一の血縁である息子(亡くなった姪の忘れ形見を養子にした)のことを思い、またやり残したことや生への断ち切り難い執着で胸が塞がり哀切極まる姿にもう現実と虚構の境目は消えてしまいました。
カイウラニ・リーはレイチェル・カーソンが憑依しているかの如く、映像の中で彼女の生を生きていました。
現実と虚構の境目を超えるということ—このことは映画の本質を表しているといえます。映画の始まりのとき、リュミエール兄弟の蒸気機関車の映像を見て観客は思わず逃げそうになったといいます。観客が映画に求めるもののひとつにリアリティがあります。そもそも映画はドキュメンタリーから出発したのですから。
ポスプロによって作られた虚構のリアリティが広がる中、この映画は俳優の身体、そしてそれを真っ直ぐに捉えたカメラによってその原点に回帰したすばらしい作品だといえるでしょう。
カイウラニ・リーが長年続けてきた舞台の題名は『センス・オブ・ワンダー』、レイチェル・カーソンの著作の題名でもあります。
みなさんも感性と想像力の翼を拡げていま一度映画の原点に向き合ってみてください。