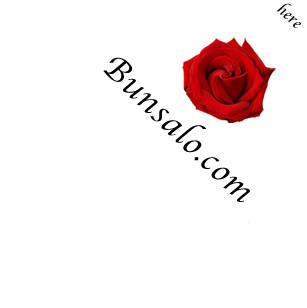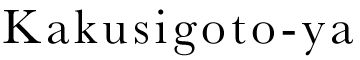羽田野直子です
青山真治監督の『東京公園』を見てきました。
かすかにタレント色をまとったキャストを見て「はてさて…」とスクリーンに向かいましたがそんな懸念は映画が始まってすぐに払拭されました。
TVで見たことのない三浦春馬が榮倉奈々が、見事にそこで自然に生きていたのです。
亡き母の影響で写真家を目指している大学生、光司がひょんなことからある歯科医の男性にたぶん妻であろう女性が幼い娘を連れて毎日都内のどこかの公園で遊ぶ姿を写真に撮って送って欲しいと依頼されます。
光司、そして彼を取り巻く3人の女性—歯科医に頼まれた被写体である女性、親友の元カノで幼馴染の女の子、父の再婚相手の連れ子で血のつながらない9歳年上の姉—が絡まりながら話は展開していきます…といってもいわゆる、何か決定的な事件が起きたことで誰かの人生が大きく動き出すというような類のことは一切ありませんが。
これは死んだひとを巡る映画という言い方が当てはまるのかもしれません。
主人公の若くして亡くなった美しい母、親友、主人公のバイト先であるカフェバーの元店主。
生きている人びとは身近なひとを亡くした悲しみを共有することで束の間寄り添い、そして彼らの不在を埋めるかのように絡まりながら、でも結局深くは交わることなく淡々と時が流れていく。
ふと小津安二郎の『東京物語』を思い出しました。
題名に「東京」とあるからだけではなく、亡くなったひとを忘れないということが、ひとの心を繋げるという類似点で。
尾道から上京した老夫婦は血の繋がった子どもたちよりも、戦死した末息子の嫁と深く心を通わせる。
また帰郷後亡くなった老妻の不在をより強く思い、その悲しみを分け合う老父と末娘と末息子の嫁も然りでした。
なくしたものへの哀惜を紡ぐ映画という共通点を持ちながら、でもこの『東京公園』は現代の東京が舞台です。
誰もがひとと真っ直ぐ向き合うことに臆病で、ひとにはかなり手厳しくアドヴァイスができても自分のことはからっきし…というひとばかりです。
妻に豊かな暮らしをさせるだけの経済力と社会的地位だけが自分が選ばれた理由でほんとうには愛されていないのでは疑心暗鬼にとらわれている夫。
そしてその夫にお互いにしかわからない暗号で愛情を伝えようとする妻。
サイドストーリーである、ここだけがわずかながら一歩踏み出したように見えました。
かつて確乎としてあったはずの家族がいつの間にか壊れていた『東京物語』は見たあとでなんとも言えない悲しみが残りました。
でも『東京公園』は血縁を超えて心を寄せ合うものが「家族のようなもの」として再生していくという意味で心が温かくなる思いがしました。
そして何の変哲もない公園の日だまりが何ものにも代え難い、ひととひととを繋ぐ広場であるということにふと気づくのです。
ひとは生きていくうえで誰かを傷つけたり、傷ついたりするものです。
でもそういうことをわかり合って寄り添うことでふつふつと湧いてくる、人間の温かい幸福感が画面からほんのり伝わってきます。
あの辛い震災を目撃したあとだから余計なのかもしれませんが、映画全体からほんのり漂ってくるやさしい雰囲気にしんみり浸ったのでした。